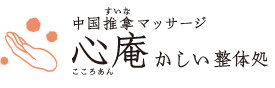お酒は「百薬の長」といわれ、適度な飲酒は胃液の分泌を亢進させて食欲を増進したり、中枢神経に作用してストレス解消にも効果があるといわれています。しかし、「大酒飲みには麻酔がかかりにくい」といわれるようにアルコールと薬は相性が悪いようです。果たして飲酒の度合いによって薬の効き方に違いがあるのでしょうか。
薬とアルコールの相互作用
■薬とアルコールの作用が重なり、薬の作用が増す場合
アルコールには中枢神経抑制作用(精神・運動機能を低下させる作用)や血管拡張作用があります。薬の効果や副作用として「眠気」の現れる薬(催眠鎮静薬、抗うつ薬、解熱鎮痛剤など)は、中枢神経を抑制するので、お酒と同時期に飲むとアルコールの作用と相まって、眠気、だるさ、注意力の低下などが一層強く出ることがあります。
また、抹消血管拡張作用をもつ高血圧治療薬では、血圧が下がり過ぎて、めまいや頭痛などが起こることがあります。
このように薬と一緒にお酒を飲んだり、飲酒後すぐに薬を飲んだ場合は、肝臓で薬とアルコールの両方を同時に処理できないため、アルコールを優先的に分解しようとします。そのため、薬の代謝は後回しになり、薬は通常より高い濃度のまま肝臓を通過し、全身に回ることになります。つまり、薬が効きすぎてしまうことになるのです。
また、アルコールを常飲している場合には、薬の分解が早まってしまうことにより、薬が効きにくくなることがありますので注意が必要です。